12年ぶりの九州、そして初めてとなる北九州で迎える朝。時刻は8時前、まだ早い時間だがこれから巡る地は見どころたっぷり。すっきりと起きられたそのままの勢いで身支度を整え、関門観光へいざ出発。

腹が減っては戦はできぬということで、まずは朝食を。というより12年ぶりとなる九州福岡、一番最初の目的地として挙げたのがここ。ずっとずっと来てみたかった、『資さんうどん』大里店へと向かいます。

席に着き、タブレットとにらめっこ。一番人気は肉ごぼ天のようだが、はじめての福岡うどんなのでシンプルにごぼ天だけもいい。いやでもそういえば、北九州ってかしわうどんが名物だったような気もする。ということで今回は、かしわごぼ天うどんとぼた餅を注文。
運ばれてきた瞬間、目が釘付けに。もう食べる前から、こんなの旨いに決まっている。まずは琥珀色の澄んだおつゆから。だしの利いた薄口、そこにふんわりと広がるほどよい甘味。そうだ、九州は甘いんだった。それが決して嫌味でなく、甘味=旨味という説を実証している。
つづいて、柔らかさが特徴だという福岡うどんの麺を。うん、確かに柔らかいことは柔らかい。でものびたりふやけたような感じではなく、もっちもっちと小麦の風味を感じる存在感。飲む点滴のような穏やかなおつゆに、この食感はベストだわ。
心身に沁み入るようなやさしいおいしさを味わい、かしわへ。細かく切った鶏肉が淡口で煮込まれており、ときおり感じる親鶏の食感と濃い風味がいいアクセント。これまたほんのり甘めに味付けされているので、食べ進むと鶏の脂や甘さがおつゆに溶けだし表情が変化。
そして待望のごぼ天。見るからに太いごぼうは驚くほど歯切れよく、硬さや繊維質などまったく感じない。この太さだからこそのほくほくとした甘味、そして鼻腔をくすぐるごぼうならではの香り。ちょっとばかり厚めの衣におつゆが染み、旨い旨いと箸が止まらなくなる。
どこまでも穏やかなうどんの旨さを堪能し、〆となるぼた餅へ。見ての通りしっかりと豆の残された粒あんは、思いがけず甘さ控えめ。ほっくりとした小豆の風味が最大限に活かされ、粒あん派の僕は大喜び。もち米も絶妙な塩梅の半殺しで、ぼた餅と残したおつゆの甘いしょっぱいの往復が堪らない。

これが福岡のうどんか。讃岐とも関西とも違うその旨さに、九州第1食目から大満足。と思いきや、後半にとろろ昆布入れるの忘れた!もうこれは、福岡リベンジ確定だな!

訪れた大里店は門司と小森江の中間に位置するため、そのまま道なりに歩いて小森江駅へ。ここから鹿児島本線に乗車し、隣の門司港を目指します。

JR九州らしい派手な電車に揺られていると、車窓には水路のような関門海峡が。対岸は下関、この距離感で本州と九州が隔てられているとは。

目の当たりにした関門海峡の狭さに驚いていると、列車は終点の門司港に到着。長大な鹿児島本線の起点、長きにわたり九州の玄関口としての役目を果たしてきました。

ホームに降り立つと、まず目を引くのが渋い上屋。木と廃レールでできており、鉄部の風合いからこれが造られたレトロではないことが伝わってくる。

昭和39年まで、関門連絡船の接続駅としての役割を担ってきた門司港駅。頭端式のホーム、広いコンコースにかけられた大きな屋根。ターミナルとして歩んできた威厳が、そこかしこに宿されている。

大正3年にこの地に移されて以来、数えきれぬほどの旅客が行き交ったであろうこのホーム。目を瞑れば、今でもその雑踏が聞こえてきそう。

並ぶ自動改札機の横には、昔懐かしい木のラッチが。僕の小学生のころまでは、これが当たり前だった。カチカチカチカチときっぷを切る音が、耳の奥へと蘇る。

九州の鉄道の起点としての歴史に圧倒されつつ、駅舎内へ。広々としたコンコース、その一画に設けられた出札窓口。かつて船から降りた人々は、長い列を作り九州各地への切符を買い求めたのだろう。

昭和17年に関門トンネルにより九州と本州は鉄路で結ばれましたが、それまでは下関から連絡船でここまで渡るのが主たるルート。大勢の旅客やたくさんの荷物が往来する姿が目に浮かぶよう。

大屋根で覆われた通路の脇には、歴史を感じさせる水飲み場が。この水道は、この駅が開設された頃からのものだそう。海外から帰還した人々が門司に上陸し喉を潤したことから、帰り水と呼ばれています。

その奥の建屋には、見るからに歴史を感じさせる洗面所。昭和4年に洗面専用として設置されたものの一部だそうで、大理石や古い蛇口が印象的。かつて動力が蒸気機関だった時代、列車を降りたらみな顔や手足が石炭のすすで黒くなっていた。そんな時代にはなくてはならない設備。

街歩きの前にとトイレに寄ってみると、その入口には立派な水場が。この駅の開設当時からあるものだそうで、戦時中の金属供出を免れたことから幸運の手水鉢と名付けられています。

構内に残された深い歴史に圧倒され、ようやく外へ。大正3年、当時の門司駅としてこの地に移されたときに建てられた駅舎。中学生の頃だったか、存在を知って以来ずっとずっと逢いたかった駅。

長きにわたり、九州の顔として現役を続ける重厚な駅舎。駅舎としては日本で初めて国の重要文化財の指定を受け、6年前には耐震化とともに建築当時の姿への復原が完成。
秋晴れの空に佇む、荘厳さにあふれるシンメトリーのターミナル。大正初期の美意識の込められた優美な姿に、しばし時を忘れ見とれてしまうのでした。




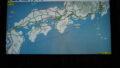
コメント